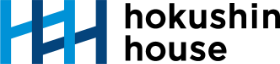
Media
メディア
新年度から早2ヶ月!収納を見直してみませんか?【リビング編】
新年度は、大人も子供も何かと忙しないですよね。新年度スタートからもうすぐ2ヶ月。慌ただしい日常にも身体も心も慣れて、ふとした瞬間に子どもの成長を感じることが多いのではないでしょうか。幼児期と学童期では、身体の大きさはもちろん生活導線も変わってきますよね。
目次
子どもの成長とともに収納の見直しを
小さかった子どもが、保育園や小学校に行くようになると少しだけですが時間に余裕を持つことができるようになりますよね。
朝、子どもの送迎やお見送りが終わり誰もいない家を見渡してみると、色々と不要なものが目につくようになることってありませんか?
遊びそうで遊ばないおもちゃ。使いそうで使わないもの。
子どもの成長とともに必要なものとそうでないものは定期的に見直しましょう。

「自分のことは自分でできる!」が叶う収納を目指そう
保育園や小学校に通うようになると園や学校での必需品が増えますよね。
忙しい朝から「ママ〜、○○がない〜!○○はどこ〜!」なんてことがないように、収納する場所はもちろん、子どもの手が届く位置に必要なものはあるか?取りやすいように配置されているか?スムーズな導線になっているか?子ども目線になって場所や位置・導線を決めましょう。

必要なものだけを厳選する
収納の見直しを始めるには、まず収納されているものを把握することから始めましょう。また、一気に全部片付けようとすると気がついたら子どもが帰ってくる時間になっていたりするので「今日はこの棚にしよう」など場所を決めてから始めましょう。やり方としては、一旦収納されているものを全部出し、次に必要なものとそうでないものに分けます。「必要でないものだけどすぐには捨てられない‥」そんな方は、しばらく押入れなどの目につかないところにしまっておいて、2週間ほどしたら捨てるか決めるでも良いでしょう。

小分けの箱を用意して見える化
必要なものを厳選したら、使用頻度ごとにグループ分けしましょう。使用頻度に分けることができたら、次はちょうどいいサイズの箱などを用意して、グループ分けしたものごとに収納しましょう。ここでのポイントは「詰めすぎない」です。余白があるといろいろと入れたくなりますが、子どもが必要なものを上手にとれるように収納することがポイントです。

使用頻度を考えてしまう場所を決めよう
次に導線と位置を考えながら収納場所を決めましょう。毎日使うものでも「朝だけ使うもの」や「帰ってきてから使うもの」など時間帯によっても分けてみることをおすすめします。また、収納場所を決めるときは、子どもと一緒に日常の動きをシミュレーションすることも大切です。場所や位置を決めるときは、どうしてもお母さん中心に決めてしまいがちですが、実際使う人と一緒に場所を決めることでより生活導線にそった収納を目指せます。

少しの手間で、散らかりやすいリビングもスッキリ
家の中にあるものを把握し、使うものと使わないものをわけ、使用頻度と生活導線を意識するだけで、モノを探す時間もなくなり忙しい朝の時間にも少し余裕がうまれますよね。スッキリした空間に身をおくことで余計な手間もコストもなくすことができるので、まずはリビングの収納見直しから始めてみてはいかがでしょうか。

